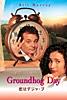【映画メモ】恋はデジャ・ブ(原題:Groundhog Day)
「1つの場所から出られず、毎日が同じ事の繰り返しならどうする?」
気象予報士の男が、ある田舎町で2月2日(グラウンドホッグデーという祭りの日)を延々と繰り返さなければならなくなるというコメディ。
どんなことをしても2月3日にはならない(目覚めると2月2日の朝に戻っている)ため、それを利用して主人公は暴飲暴食、女を口説く、強盗など欲望のままにやりたいことを一通りやります。しかし退屈な日々から抜け出すことはできない。自分だけが延々と同じ日を繰り返さなければならないことに耐えきれず自殺しても、また2月2日の朝に戻ってしまいます。
ある時から、主人公は無限に続く時間を、自分だけでなく周りの人のために使うようになります。町中の人を助けたり、ピアノを練習して披露したり。自己中心的で嫌なやつだった主人公が、周りの人から尊敬され、生き方が変わっていく…。
こんな物語です。この映画ではタイムスリップ的な超常現象により全く同じ日を繰り返すわけですが、「代わり映えしない毎日を繰り返さなければならず、抜け出すことができない」という点は、私たちの日常にも当てはまるのではないでしょうか。
家と会社を往復するだけの毎日。同じような仕事をして、同じ人に会い、同じような食事をとる。特別なことなんて滅多にありません。
冒頭の言葉は2月2日から抜け出せないことを嘆く主人公のセリフですが、私たちへの問いかけともとらえられます。「もし単調な日々が続くとしても、とにかく全力で楽しみたいことや挑戦したいことがあるのか?」と。
私は最近、モチベーションが上がらず、「特にやりたいこともない」という状態が続いてます。しかし考えてみると、映画の中で主人公がピアノを練習したように、「時間があったらやりたい」と言いながら本気でやろうとしていないことがいくつかあります。映画と違って時間は限られていますが、そういったことを手当たり次第やってみるといいのかなと思いました。あと、時には欲望のままに動いてみるのがいいかもしれない。
結局は一日一日を精一杯楽しむこと、自分から変えようとする姿勢がなければ退屈な日々から抜け出すことはできない。そういうことを改めて実感させてくれる映画です。
結局は一日一日を精一杯楽しむこと、自分から変えようとする姿勢がなければ退屈な日々から抜け出すことはできない。そういうことを改めて実感させてくれる映画です。
Kindle愛用者だが、紙の本のメリットについて書く
しかし最近になり、紙の本を買うことも多くなってきている。読みたい本の電子版がないわけではなく、紙版も電子版もあるが、紙の方を選んでいるのである。
そこで、最近感じている紙の本のメリットについてまとめてみたい。
そこで、最近感じている紙の本のメリットについてまとめてみたい。
本題に入る前に、電子書籍のメリットを挙げておこう。
- 読み終わっても場所をとらない
- 大量の本をコンパクトに持ち運び可能
- 読みたい本の電子版があれば、一瞬で買える
- 紙版より電子版の方が安い。Amazonならポイント還元セールもある
- わからない単語をすぐに端末の辞書で調べることができる
では、紙の本のメリットを書いていく。
全体像を把握して「拾い読み」ができる
限られた時間で本を読む場合、本のエッセンスを見つけ、「拾い読み」することは大事だ。本をパラパラめくって拾い読みしたり、目次を読んで面白そうな箇所だけ読んだりすることができるのは紙の本の大きなメリットだ。
拾い読みは、特に軽めのビジネス書や、すでに知識のある分野の本を読むときに有効である。
Kindleでも目次から特定の章に飛ぶことができるものの、ピンポイントにその箇所へ飛ぶだけなので、本全体の位置づけや前後の章との関連性などが直感的にわかりにくく、紙の本ほどスムーズな拾い読みができない。
大事な箇所を後で参照しやすい
私は本を読んでいて気になった部分には付箋をペタペタ貼っている。こうしておくと、読書記録などを書くときに便利だ。何度も読み返す価値のある本であれば、付箋を貼った箇所を読み直すだけでかなり定着率は良くなる。
Kindleには「しおり」やハイライト機能はあるが、しおりの箇所に飛ぶのもやや手間である。とくにしおりがたくさんになってくると参照するのが面倒だ。Kindleをものすごく使いこなせば変わってくるのかもしれないが…。
電子書籍よりも「後から参照しやすい」という点も紙の本のメリットだ。
紙の本の方が早く読むことができる(気がする)
紙をめくって読み進めるほうが、電子書籍の画面の切り替わりに比べてリズムよく、早く読める。これは正直個人的な感覚でしかないのだが。少なくとも「電子書籍の方が早く読める」という人はいないのではないかと思う。
読み終わったら捨ててしまえば場所をとらない
紙の本の場合、場所をとってしまうのは確かだし、私もこのデメリットが一番のネックだった。しかし、後から読み返したくなるほどの本は、せいぜい年に数冊程度だ。
そのため、読み終わったら躊躇なく捨てる、または売りに出せばよいと考えるようになった。万が一あとで読み返したくなったら、それこそ電子書籍で買えばいい。
そのため、読み終わったら躊躇なく捨てる、または売りに出せばよいと考えるようになった。万が一あとで読み返したくなったら、それこそ電子書籍で買えばいい。
中古本を買えば電子版より安い
中古本はだいたい電子版よりも安い。Amazonなどで実物を見ずに中古本を買うのには抵抗があったのだが、買ってみると予想以上にきれいで、新品同様のレベルであることも多い。商品の状態が「非常に良い」、「良い」など出品者の情報をよく確認することが重要。
おわりに
紙向きの本
- 参考書、専門書:特定の箇所を後で参照することが多いため、すぐに参照しやすいほうが便利
- ビジネス書:全部読んでもいいが、拾い読みできると何かと便利
電子書籍向きの本
- 漫画、小説:基本的に、読んでいる途中で前の箇所に戻ることが少ない
- 洋書:わからない単語をすぐ調べることができる。洋書は紙だとデカくて重すぎる